千葉県柏市で、地元に伝わり今も残る「昔話」は40を超えるそうです。
一つの市でここまでたくさんの「昔話」が残っているのは、伝えられていた話をずっと昔の方が一冊の本にして代々残していたからだといいます。
現在は、昭和60年に柏市教育委員会が発行した本によって語り継がれていて、昔話自体は現在、柏市のホームページで見ることが出来、柏市観光協会でもピックアップして現地で聞けるQRコード看板の仕掛けも。
そんな身近な地元の昔話を読んで、実際のお話に出てくる場所へ行ってみて、更に柏市図書館の書籍でも伝説の人物の真実を追ってみました。
「地獄から戻ったお姫様」かんたんに
むかしむかし、平将門さまにとても美しいお姫様がいました。
そのお姫様は、お地蔵様が大好きで、とても大事に信仰していたそうです。
やがてお姫様は病気になり亡くなってしまい、地獄に落されてしまいます。
地獄で苦しむお姫様の前にお地蔵さまが現れて、ここはあなたが来るようなところではありませんと言って現世に戻してくれました。
生き返ったお姫様は、ますますお地蔵様を大切にして、自分の名を「如蔵尼(にょぞうに)」と名乗り、父である平将門さまと一族の供養を続けました。
如蔵尼が父を弔ったといわれる岩井の地蔵堂は今も龍光院に残ります。
龍光院と将門神社
この物語の舞台である柏市岩井にある龍光院様へ行ってみました。
私(筆者)の休日いつものサイクリングコースで、手賀沼沿いで道の駅しょうなんまで行き、そこから住宅街に少し上ったところ。
真言宗豊山派でご本尊は不動明王です。
境内には、物語に出てくる如蔵尼が地蔵尊を崇敬したといわれる地蔵堂がありました。
この堂の中の地蔵尊像ですが、江戸初期に岩井村が全焼する火災があり、その時にはひっそりと姿をくらませており、お寺が建て直された後、別の場所で見つかった話があるとお寺の管理人さんからお話を聞きました。
そんなお話からも、火災を免れた地蔵尊ということで、火災避け(火難除)のご利益があると大切にされています。

山門入って右手奥にある地蔵堂。
四つの屋根面を持つ「寄棟造(よせむねづくり)」の小さな美しいお堂。

柏市観光協会さんの昔話看板が特等席にありました!
平将門の伝説
柏市に将門神社があったなんて、今更ながらに驚いたのと同時に、平将門ってどんな人物だったのだろうと少し調べてみました。
平氏で思いつくのは、平清盛かもしれません。
平清盛と平将門って・・?
平将門が生きたのは900年代、一方で平清盛が生きたのは1100年代だと言われており、この差は約200年になります。
どちらも平安時代の人物ですが、将門は平安時代中期で清盛は鎌倉時代寄りの人物と、同じ平家ですが、かなり離れています。
平将門は、関東地域で起こった平氏一族の内紛「将門の乱」で戦に勝ち続けました。
勢いにのった将門は京都の朝廷だった朱雀天皇に対抗して「新皇」を名乗ります。
その後、朝廷から朝敵とされて朝廷軍と戦うことになり、敗れてしまいます。
柏市を含む旧相馬郡を支配した相馬氏が将門の子孫だったと言われることから、将門を英雄として崇拝する民衆がこの地に多かったという説も。

龍光院の将門神社。
柏市に将門神社があることを知らない柏市民もきっとたくさんいるはずです。
如蔵尼は伝説の滝夜叉姫なのか
平将門の娘といえば、妖術使いの伝説が残る滝夜叉姫が有名です。
正確にいうと妖術使いの滝夜叉姫は「瀧夜叉姫」とも言われ、こちらは京都の貴船神社で妖術を授かり、父のリベンジを果たそうとしたようです。
一方で柏市の昔話に残る如蔵尼も将門の三女=滝夜叉姫ですが、彼女は復讐というよりも父と一族の供養に一生を捧げた話が残ります。
滝夜叉姫のお話は福島県や茨城県にも残されていますが、将門にしても滝夜叉姫にしても1,000年以上前の人物ですので、真実は秘められたままです。
ですが今回龍光院様へ行ってみて、お寺に並んで将門神社があることと、お寺の境内にある如蔵尼の地蔵堂を見て、平将門とそのお姫様の存在を遠い昔のこの地に感じることができた気がします。
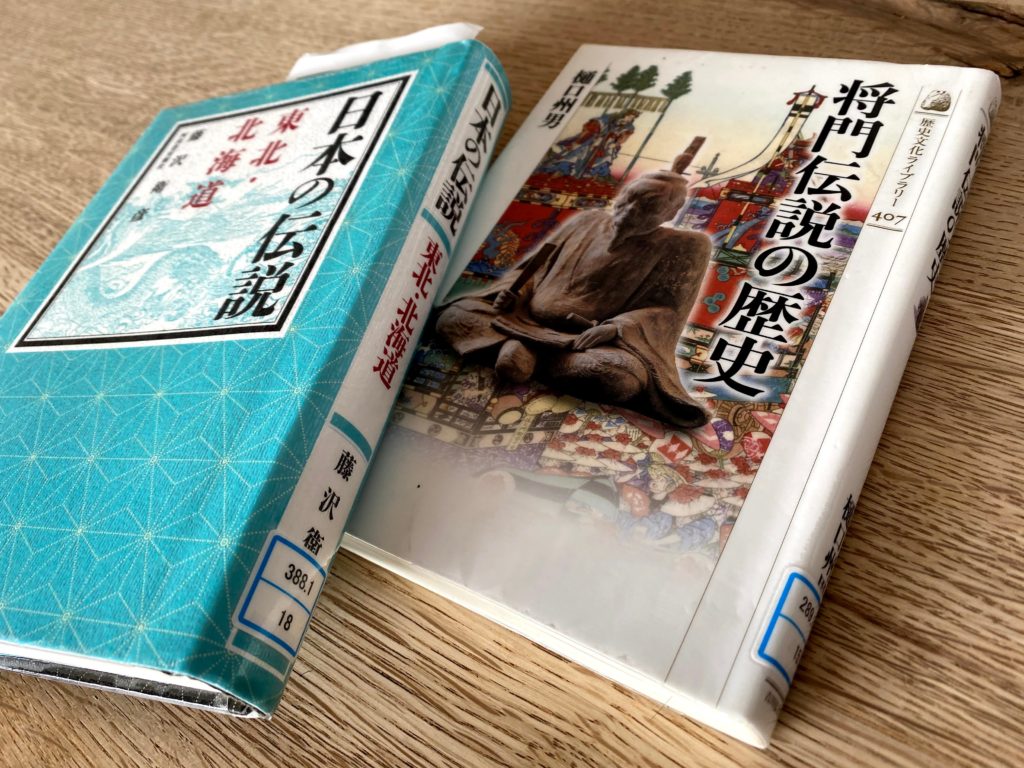
今回、龍光院の帰りに柏市図書館で借りた書籍。
・将門伝説の歴史:樋口州男
・日本の伝説 東北・北海道:藤沢衛彦
最後に「地獄から戻ったお姫様」
柏市の昔話では、地名や実際のお寺の名前が残っているお話も多くあります。
普段あまり行くことはないけれど、昔話を読んで舞台となった場所を知り、歴史を少しだけ調べてみる。
とっても小さな旅行と、ほんのちょっとの勉強だけど、これだけで週末が楽しく過ごせた気がします。
現地で貴重なお話を聞けるときもあれば、お話はなく、そこにはロマンを感じさせてくれる建物や跡地だけがある。
そのとき、そのときの楽しみ、出会い、そんな毎日を大切にしていきたいと感じます。
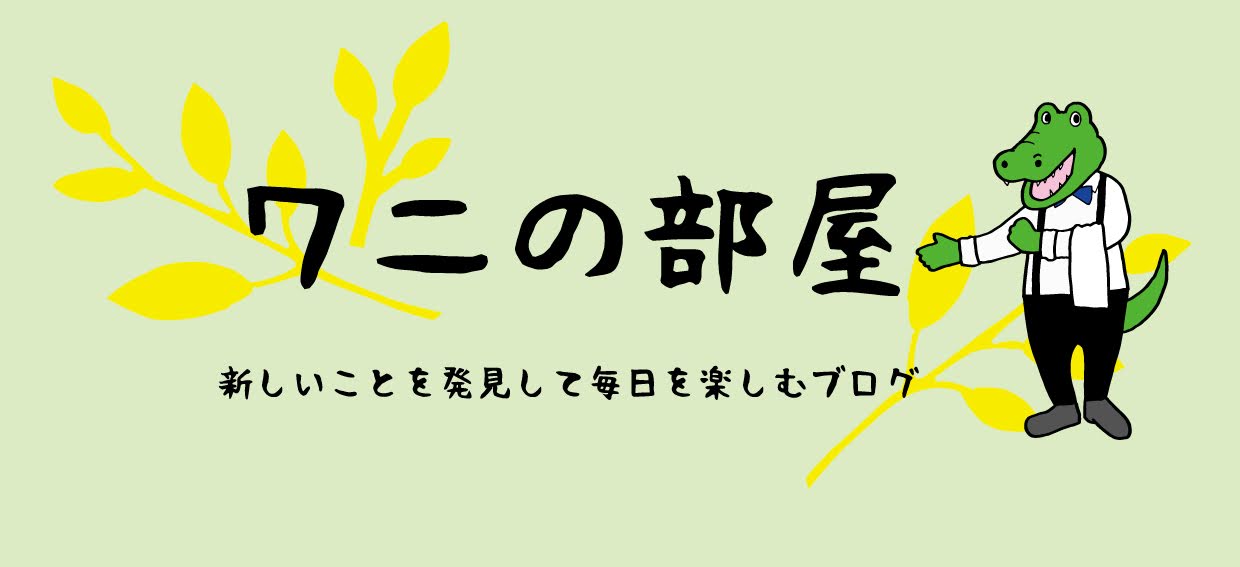



コメント